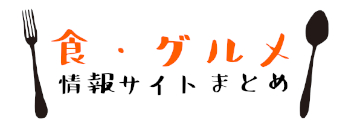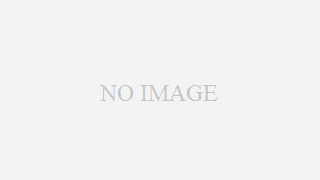通るたびに気になっていた“ど真ん中な中華”の存在

神田駅東口からほど近く、神田駅東口一番街通りにある「北京料理 東園」。以前から店の前を通るたびにその存在が気になっていた。
昨今街中でよく見かけるギラギラとした大陸系の中華料理店とは対照的な、いかにも歴史ある店構え。かといっていわゆる「町中華」とも明らかに異なる落ち着いた佇まい。
店頭に張り出されたメニュー表の価格だけを眺めると、決して高級店というわけではないこともわかる。もちろんチェーン店でもなければ、本場志向のマニアックな店というわけでもない。
こういうお店をどう呼べばいいのだろう。今やさまざまな業態がひしめき合う中華の世界で、ある意味ど真ん中にある店だ。だから、何も付けず単に「中華」と呼べばいいのかもしれないが、実はど真ん中と言いながらこういう店は今となっては数の上では決して多くはない。むしろ貴重だ。
だから私はこういうポジションの店を便宜的に「ちょうどいい中華」と呼んでいる。中華料理の代表的なメニューはひととおり揃えていて、気楽にランチを食べに行くこともできるし、「今日は誰かとゆっくりおいしいご馳走を食べたい」というちょっと特別な夜にもその期待に応えてくれる、そんな王道の中華料理レストラン。
クラシカルな外観と、極めて“今どき”なメニューのコントラスト
「東園」が単に「ちょうどいい」だけの店ではない、ということは、初めてこの店を実際に訪れたときに気づいた。外観からは思いもよらないモダンで綺麗な内装にも少し驚いたが、特徴的なのはなんといってもメニューだ。
メニューはもちろん昔ながらの王道中華料理が中心なのだが、そのいたるところにオリジナリティが散りばめられている。
銘柄豚や国産牛、フカヒレ、季節によっては上海蟹など、素材へのこだわりは高級店にも引けを取らない。それだけでなく、山伏茸やアワビ茸、江戸菜など、個性的な野菜を使ったヘルシーメニューが全面的に打ち出されている。
そのことが物語るように、料理はどれも素材重視の上品な味付け、かつ丁寧でヘルシーな仕上がりだ。
あえてざっくりとした言い方をすると、「東園」の料理はそのクラシカルな外観に反して極めて「今どき」なのである。最近一部で注目されている、若いオーナーシェフによるコース料理主体の「ワンオペ中華」の軽やかで洒落た料理にもどこか通じるところがある。それもあってか、ここでは若い女性の1人客もしばしば見かける。
もちろんお客さんの中心は、おそらく昔から通い続けているのであろう近隣の男性ビジネスマンたち。餃子、エビチリ、酢豚といった定番とともにビールの杯を重ね、最後は麻婆豆腐をライスにかけてがっつく、そんな光景もよく見かける。

見切り発車で始まった老舗の歴史
こんな、王道の老舗でありつつ同時にモダンで個性的な中華料理店は、どのような歴史を辿って今ここに到達したのだろう。社長の小林慎一朗さんにお話をうかがってみた。創業者である小林忠義さんの息子さんだ。
「創業は1961年。私が生まれた年です。父親はそれまで秋葉原のデパートの中で蕎麦屋をやってたんですが、あるとき、そこを出なきゃいけなくなって。そのとき、たまたまこの場所が中華料理屋の居抜きで売りに出てて、一念奮起して買い取ることを決めたようです」
それまで蕎麦屋しかやったことがなかった忠義さんだったが、店は設備だけではなく従業員もまだ残った状態で売りに出されており、「なんとかなるだろう」という見切り発車だったようだ。
ただし、当時の東園のスタイルは今とはだいぶ異なる。基本的には出前が中心の店だった。なので扱うものは麺類や丼物、定食が中心。カツ丼やオムライスもあったという。そう、まさに典型的な東京下町スタイルの、今の言葉でいう「町中華」である。時代はそのまま高度経済成長期に突入、店は出前だけでも充分すぎるほど儲かったという。
現社長の慎一朗さんは、ファミレスチェーンの会社で経営を学んだ後、新宿の高級中華料理店での修行を経て1984年に入店した。そのまま父親との二人三脚で出前の町中華を続けてそのまま跡を継ぐ……かに見えたが、実は父親には別の腹づもりがあった。
父親の忠義さんは将来息子に店を継がせるにあたって、「こんな商売は継がせられない。もっとやり甲斐のある仕事でなければならない」と考えていたのだ。時代はバブル期、東北新幹線の開通もきっかけに、神田の街は大きく変化しつつもあった。忠義さんは木造2階建てに屋根裏部屋付きだった店舗を立て替えることを決意する。「これからは出前の時代ではない。もっとしっかりとした料理を出し、宴会や会食をとっていかねば」と考えたのだ。新しい建物の2階には廻る円卓のある個室をしつらえた。
「宴会が取れなかったら? なあに、その時は従業員の休憩室に使えばいいさ」
忠義さんはそう言って笑っていたそうだが、その実それは大勝負である。
お客さんが来てくれるかどうかも不安だっただろうが、それ以上にもっと不安なこともあった、と慎一朗さんは回想する。この大きな方向転換に従業員たちはついてきてくれるだろうか、と。しかしその心配は杞憂に終わった。誰もがこの方向転換を歓迎し、修行帰りの慎一朗さんに「いろいろ教えてください」と目を輝かせたという。慎一朗さんは習いおぼえた宴席中華をコックさんたちに教え、東園の第二期がスタートした。
時代もちょうどよかったのだろう。建て替え後の新生東園は滑り出し上々だった。それだけで当時1日で10万円の売り上げがあったという雀荘の出前だけは改装後もしばらく続けていたが、いつしかそれもやめてしまった。あっという間に、日々の宴席をこなすだけで精いっぱい、という状況になったのだ。
しかし当時の東園に関して慎一朗さんはこう語る。
「正直、当時の料理はそうたいしたものじゃありませんでした」
謙遜ともとれるが、この言葉はもしかしたらそのままとった方がいいのかもしれない。なにしろコックさんたちはそれまで「(今でいう)町中華」の料理しか作ったことがない。そのコックさんたちに教える立場の慎一朗さんも、高級店での料理修行は1年かそこら。それでもなんとかなったのは、バブルという時代ゆえだったのかもしれない。そしてそれに甘んじているだけだったら、この店はバブルと共に心中する運命にあったかもしれない。
しかしそうはならなかった。
「若かったし、とにかく夢中でしたよ」と、慎一朗さんは語る。当時から慎一朗さんには明確なポリシーがあった。ホテルや高級店に負けない料理を出したい。街場の他の中華料理店とは明確に差別化しなければいけない。素材にこだわってヘルシーで現代的な料理にしていかなければならない。
「だからあらゆることにチャレンジしました」。
慎一朗さんのチャレンジを繰り返し、常にアップデートを欠かさない姿勢が現在の東園を作り出したし、それは今も続いている。
飛び込み営業された青菜を生でガブリ…メニュー採用を即決
あるとき、1人のスーツ姿の巨漢が巨大な青菜の束を抱えて店を訪れた。おしゃれな都会人である慎一朗さんは「この人絶対普段はスーツ着慣れてないだろうな」と直感したという。巨漢氏は「とりあえずこれ食べてみてください。生で!」と慎一朗さんに詰め寄った。その新鮮な青菜をパキッとかじった慎一朗さんは、即座にその野菜の素晴らしさを理解した。聞くと巨漢氏は自ら栽培した野菜を抱えて慣れない営業回りをしているとのことで、慎一朗さんはすぐにそれをメニューに取り入れることにした。
その野菜こそが今やブランド野菜として一世を風靡している「江戸菜」である。
またあるときは長野のきのこメーカーの営業マンが、生産を始めたばかりの新顔きのこを持って飛び込みで訪れた。
「このきのこ、ご存じですか?」と得意げにそれを差し出す営業マンに、慎一朗さんはこともなげに「山伏茸でしょ」と返して営業マンを驚かせた。研究熱心な慎一朗さんは既に山伏茸の料理を研究しており、それが現代的な中華に実にマッチした食材であることを見抜いていた。そのときは仕入れの一塊があまりにも巨大で、また鮮度落ちも早く、メニューに組み込むことは断念した経緯があった。メーカーが本腰入れて生産するなら、と、それ以来、山伏茸は東園になくてはならない食材となった。きのこメーカーからはその後も、新顔のきのこが出るたびにそれが東園に持ち込まれる。
そんな慎一朗さんには、料理人として強烈な原体験があった。それがかの伝説的なTV番組『料理の鉄人』である。
「それまで、料理人や飲食店は世間の中でも下に見られるもの、と思い込んでました」と語る慎一朗さんの実感は、家業である庶民的な出前中華の商売を物心ついた時から眺めていた立場からすると、とてもリアルで切実なものだったことは想像に難くない。
「しかしあの番組を見て、料理の仕事って本当はかっこいいんだと気づきました。プライドを持って一生取り組める素晴らしい仕事だと」
それは創業者である父親の「息子にはやり甲斐のある仕事を継がせたい」という当時の思いとも見事なまでにリンクしている。
「改善魂」がこの状況でさらに加速する…!
第二期の「宴席中華」東園はその後、職人たちが入れ替わるなかでさらに腕のいい職人が入ってきて、料理はますます進化する。こういう世界においては、腕のいい料理人ほど短期間で数多くの店を渡り歩くのが常だ。しかし彼らはなぜかこの東園ではじっくり腰を据える。常にアグレッシブに前進を続けようとする慎一朗さんへの共感と信頼が彼らをそうさせているのではないか。そう私は思った。そしてそんな現在の東園について慎一朗さん自身が胸を張る。
「東園の長い歴史の中で、間違いなく今が最高のクオリティです」
未熟な自分が料理を教えていた改装当時は大したことなかった、と述壊する40年前から、店とその料理は確実に進化してきたというプライドだ。この店に通い始めてから半年にしかならない私から見ても、そのプライドには確たる根拠があると思う。あえてベタな言い方をするならば、東園は「町中華とそう変わらない価格で高級中華に勝るとも劣らないクオリティやオリジナリティを実現している店」である。
「不謹慎かもしれませんが、コロナはチャンスだったのかもしれません」
慎一朗さんは唐突に語った。
「もちろん経営的には極めて厳しい。かといって従業員を解雇はしたくないし給料も落としたくない。でもコロナは『変わるチャンス』でもありました」
コロナだからこうしよう、と改善を提案したら誰も反論できませんよね、と慎一朗さんは冗談めかして笑う。そのキャリアをずっと貫いてきた「改善魂」が、ここに来てさらに加速した、ということか。
例えば2人連れ、3人連れのお客さんがアラカルトで何品かをオーダーすると、東園ではその料理を全て人数分に分けて提供してくれる。ホテルなどの高級店ではいざ知らず、街場のこの価格帯の店では相当珍しい。もちろんきっかけはコロナ下で「シェアの自粛」から止むを得ず始まったサービスではあるが、この店の繊細な料理において、それはさらに料理の質を高める。中華、ことにとろみのあるあんを絡ませた料理などは、取り分けの仕方ひとつでずいぶん味が変わるものだ。
もちろんそれは厨房に負担をかけるサービスでもある。だから慎一朗さんは最初、自分とホールスタッフがその取り分けを行うことにした。しかしそのうちなんとなく、コックさん自らがそれを行うようになった。
「見ちゃいられねえ、と思ったんでしょうね」と、慎一朗さんは笑う。
そんなコックさんたちも、「このサービス、コロナ終息した後も続けます?」と慎一朗さんに問う。慎一朗さんは「ああ、続けるよ。お客さんすごく喜んでくれるからね」と返す。
「ですよね」と苦笑するコックさん。
コロナ下では食材の質もむしろ上げた、と慎一朗さんは言う。

この店のふかひれ姿ラーメンは驚愕だ。やや小さめとはいえ、姿のままのフカヒレが丸々1枚乗っかってなんと1,800円。格安にも程がある。これも実はコロナ下に始まったメニューだ。会食用の高級食材が全く売れなくなった中華食材屋さんの苦境を見かね、東園では保存の効くそれをごっそりと仕入れた。長時間かけて丁寧に煮込み、自慢のスープをしっとりと含ませる。

牛肉はもともと国産牛を使っていたが、コロナ下でそれを思い切って和牛赤身肉に変えた。
「国産牛も充分美味しかったんですが、一流のステーキ屋さんみたいな『感動』とまでは行かなかったから」と、その理由を語る慎一朗さん。初めてその牛肉を使って料理したコックさんたちも、あまりの違いに仰天したそうだ。しかしもちろん原価は跳ね上がり、それまで1,200円だった牛肉のトウチ炒め(まあそもそもそれが安すぎるという話でもあるが)は2,000円に値上げされた。
「それでもこういう時代だからこそ、感動レベルの料理を出さないと」
そう語る。
感動レベルの料理を出せるかどうかが飲食店の命運を分ける
もしかしたら東園は、コロナ禍を経て「第三期」に突入しようとしているのかもしれない。バブル時代の追い風も味方して「宴席料理」は東園を支えてきたが、今後コロナが終息したとしても「会社の宴会」「接待」「会食」などの市場は絶対に元には戻らない。これからは、本当においしいものを食べたい人たちが本当においしい店を支える「個人の時代」だろう。単に無難なだけではなく、感動レベルの料理を出せるかどうかが飲食店の命運を分けるのだ。
そんなどこまでも進化を止めない「東園」ならではの料理を実際にいくつかご紹介していこう。
餃子(6個) ¥660

まずはその美しさに目を奪われる。噛めばもっちもちの皮からパンパンに詰まった具が溢れ出す。実はこの料理だけは、レシピそのものは60年前の町中華時代から変わっていない。ごくごくオーソドックスな味わいだ。しかしもちろんこういう料理こそ、職人の気構えと指先ひとつで大きく変わる。少なくとも現在のこの餃子は「とりあえず餃子」などとコールするのは失礼な、堂々たる一品料理だ。実は特注の皮を作っているのは今をときめく「浅草開花楼」。有名になるずっと昔からの付き合いだ。

この歴史ある餃子に「よろしければご一緒に」と添えられるのが「食べるラー油」。そこはなんとも今どきだ。このラー油はどうやって生まれたんですか? と聞くと、「いや何、桃屋のヒット商品を真似しました」という思いも寄らぬ答えが返ってきて、私は腰が砕けた。
当時慎一朗さんは、「ネットで検索して」「再現レシピを片っ端からかき集めた」という。そしてそれをチーフコックと共に試行錯誤の末オリジナル商品として完成させた。改善のためならあらゆる情報を駆使する、というある種の執念が生み出した奇跡かもしれない。
貝柱とヤマブシタケのあっさり塩味炒め ¥1,650

山伏茸は、ふわふわとシャキシャキが共存する食感が魅力。そしてその細かい繊維状の傘が、味をこれでもかとたっぷり抱き込む。この特徴はこの店の上品な味付けとは特に相性がいい。
ごく繊細な火入れホタテ貝柱のおいしさはもちろんだが、その旨味を吸い切った山伏茸がすっかり主役を食う活躍ぶりである。そして貝柱同様「これしかない」という火入れの色鮮やかな野菜たちが華を添える。調理技術もさることながら、野菜そのものの品質の高さも(この料理に限ったことではないが)抜群で、市場で最上級のものをかき集めているとしか思えない。
「ウチ、八百屋さんへの支払いが毎月とんでもないんですよね。そこはチーフが妥協しないから」と、社長が苦笑するのもむべなるかなである。
牡蠣と岩海苔の炒め(10月~4月)5個入り ¥1,320

毎年恒例のシーズンメニューだが、この記事が出る頃ならまだギリギリ間に合う。常連客がこぞってオーダーし、私自身もこの店を訪れるたびにほぼ毎回注文してしまう一品がこれだ。
味付けは至ってシンプルで、ある意味中華料理らしさは強調されていない。あくまで素材感重視という趣の、いかにもこの店らしい仕立てだ。甘味や過度のうま味を加えず、ほぼ醤油と海苔自体の塩気だけで一本勝負を決めるストロングスタイルを、牡蠣そのもののミルキーな滋味がふんわりと包み込む技アリな一品。
ちなみにこの料理を作り出したのは前任のチーフコック。彼が辞めるにあたって慎一朗さんは、「この料理、あなたがいなくなった後も出していい?」と、おうかがいを立てたそうだ。もちろんチーフコック氏は快諾し、この料理はいつしか東園の名物となった。
ハーブ豚の角煮 江戸菜添え ¥1,320

いわゆるトンボーローだが、ここにもやはり東園の東園らしさが横溢している。トンボーローといえば茶色くこってりとした仕立てが一般的だが、こちらのそれは拍子抜けするほど淡い色合い。もちろんだからと言って味気ないなんてことは一切ない。肉はいたずらに柔らかく煮込まれることはなくあくまで肉肉しさを残した加減。その肉そのもののどっしりとした旨味をシンプルなあんが引き立てる。どこかフレンチの煮込みのようでもある。
その味わいを引き締めるのが江戸菜。青臭さやエグ味はないのに、微かにピリッとした新鮮なアブラナ科野菜ならではの辛味が感じられる。それこそフレンチにおけるマスタードのような役割と、箸休め的なシャキシャキした食感が共存している。まさに組み合わせの妙。
ふかひれと山伏茸と干し貝柱の蒸しスープ ¥980(要予約)

フカヒレは、それそのものに特別味があるわけではない。食感が命とも言えるわけだが、食感が心地よい食材は他にもいくらでもある。さりとてフカヒレは言わずと知れた高級食材。スープに余程の自信がなければ扱えない食材でもある。
逆にいえばフカヒレはスープのおいしさを担保するということなのだが、もちろん東園のスープもこの期待にしっかり応えてくれる。
スープは鶏ガラを中心に少しの豚ガラと香味野菜、というオーソドックスな清湯(チンタン)。それ自体はシンプルだが、器ごと蒸した具材の旨味がしみわたる。
このスープは要予約だが、メニューには常時「蟹とフカヒレのスープ」もあり、今なら前述の姿煮入り「フカヒレラーメン」もおすすめだ。
街中にひっそりと佇む「ちょうどいい中華」の、「ちょうどいい」を遥かに超えた気概と実力。中華業態乱立の今こそ、その尊さを丁寧に、そしてがむしゃらに味わい尽くしたい。
紹介したお店
🍴WEB予約してスープや牡蠣を楽しもう🍺
※本記事に掲載された情報は、取材日時点のものです
※電話番号、営業時間、定休日、メニュー、価格など店舗情報については変更する場合がございますので、店舗にご確認ください

鹿児島県出身。京都大学卒業後、食品メーカー勤務などを経て円相フードサービスを設立。多ジャンルの飲食店を経営する傍ら、食文化に関する著書も手がける。最新刊に『人気飲食チェーンの本当のスゴさがわかる本』(扶桑社刊)
Source: ぐるなび みんなのごはん
「ちょうどいい中華」だと思ったら「ちょうどいい」をはるかに超えてた―― 神田「東園」の尊さは丁寧に味わうべし