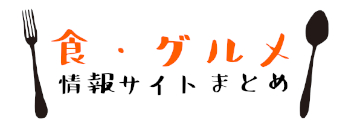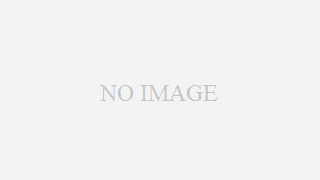インド・ネパール店のすごい本が出た
調理器具や食器の輸入販売を手がける会社「アジアハンター」の小林真樹さんが、2019年5月に上梓した『日本の中のインド亜大陸食紀行』には、インドとその周辺諸国(ネパール、バングラディシュ、パキスタンなど)出身者が経営する料理店や食材店、国内に点在するコミュニティ、さらには一般家庭への潜入取材など、膨大かつマニアックな情報がこれでもかと詰め込まれている。
この本だけでも強烈な存在感なのだが、2022年3月に発売された新刊『日本のインド・ネパール料理店』は、よりジャンルが狭く、より行動範囲が広く、そして情報量的にも物理的にも厚い本となっている。なんと480ページでフルカラー。
 左が『日本の中のインド亜大陸食紀行』、右が『日本のインド・ネパール料理店』。どちらも阿佐ヶ谷書院から発売中。
左が『日本の中のインド亜大陸食紀行』、右が『日本のインド・ネパール料理店』。どちらも阿佐ヶ谷書院から発売中。
インド・ネパール料理店といえば、この本の表紙にあるような大きなナン、ターメリックライス、カトリ(ステンレスの丸い容器)に入ったカレー、タンドリーチキン、オレンジ色のドレッシングがかかったサラダという、安心感のある定番セットを出すお店という印象で、平均的な満足度は高いけど素人目には店ごとの違いがあまり見えてこない。
そんな誰も深掘りしようとしなかったジャンルをあえて掘り下げまくったのはなぜなのか。本にも登場する巣鴨の個性派ネパール料理店「プルジャダイニング」で、じっくりと小林さんから伺った。
 巣鴨の本場ネパール料理の店、プルジャダイニング。
巣鴨の本場ネパール料理の店、プルジャダイニング。
 伝統的なネパール料理が看板メニューで、知らない料理がたくさんだ。
伝統的なネパール料理が看板メニューで、知らない料理がたくさんだ。
なぜあえて「日本のインド・ネパール料理店」の本を出したのか
小林真樹さんといえば、インドおよび周辺諸国での豊富な放浪体験をベースに持ち、日本国内でも私だったら入ることを躊躇するような店やコミュニティに精通する行動力の持ち主。
そんな人がなぜ今、インド・ネパールの料理店、通称インネパ店を取り上げようと思ったのか。
 インドをはじめとする南アジア各地の食器、調理器具を輸入販売している「有限会社アジアハンター」代表の小林真樹さん。南アジア料理に関する造詣が深く、日本人だけでなく外国人からも新規開店の相談、食器の手配相談を受けるなど絶大なる信頼を受けている。東京都出身。
インドをはじめとする南アジア各地の食器、調理器具を輸入販売している「有限会社アジアハンター」代表の小林真樹さん。南アジア料理に関する造詣が深く、日本人だけでなく外国人からも新規開店の相談、食器の手配相談を受けるなど絶大なる信頼を受けている。東京都出身。
小林 「最初に『日本の中のインド亜大陸食紀行』を出しましたが、日本の、とは言いながらも、北はせいぜい札幌どまり、南も那覇くらいしかいっていなかった」
――十分だと思いますけど。
小林 「それなりに充実感はあったけれど、よくよく考えたらもっとさらに奥、最北端は稚内、最東端なら根室、南に目を転じれば宮古島にもネパール人の店がある」
――日本の端にあるのはインド人じゃなくてネパール人の店なんですね。
小林 「インド料理も出すネパール人の店。いわゆるインネパ店。インド亜大陸からたくさんの人が来日していますが、突出してネパール人がアグレッシブ。ある種の開拓者精神に溢れていて、日本全国の『こんなところで!』っていう場所にも店を出している。インド人はあまりそこまで貪欲じゃない。
そういう取りこぼしている店がまだまだありそうだなと感じていて、機会があったら回ってみようと考えていました」
――機会があったらって思うことは多いですけど、だいたい機会がこないままです。
小林 「やっぱりコロナ禍だったというのもあります。毎年海外まで仕事の仕入れに行っていたけど、それが全部なくなってしまった。一方国内ならGo To トラベルなどを利用して、安く旅行できる期間があった。だったら今のうちに日本各地を回ってみようかなと」
 注文は全部小林さんにお任せした。左の女性が店主のプルジャさんで日本語ペラペラ。
注文は全部小林さんにお任せした。左の女性が店主のプルジャさんで日本語ペラペラ。
 いわゆるインネパ系とはだいぶ異なるメニューのようだ。
いわゆるインネパ系とはだいぶ異なるメニューのようだ。
 カレーはあるけどナンはない。小林さんはこの店でしか食べられないグンドゥルックスペシャルを注文(3/21で終了)。この店は日本で初めてディドを出したといわれているとか。
カレーはあるけどナンはない。小林さんはこの店でしか食べられないグンドゥルックスペシャルを注文(3/21で終了)。この店は日本で初めてディドを出したといわれているとか。
 マンゴーラッシーのあるソフトドリンクメニューにうっすら感じるインネパ感。
マンゴーラッシーのあるソフトドリンクメニューにうっすら感じるインネパ感。
小林 「最初は漠然と東西南北の端にある店にいきたいなくらいで、本にすることは考えていませんでした。とりあえず最北端の稚内を目指し、そこから道内を食べ歩きながらオーナーに話を聞いていたら、2004年に来日したラジャン・ギリ氏が、当時ネパール人の多かった名古屋から単身小樽市へと渡り、道内にギリ一族の店を増やしていった歴史がわかってきた」
――誰も知らない雑学ですね。
小林 「たまたま最初に訪れた北海道で、一人一人に会って話を聞くと、それぞれ北海道に対する想いとか、慣れない雪や知り合いがいない苦労を語ってくれる。競馬の厩舎で働くインド人スタッフの派遣業をやってるのがネパール人なんていう、知らなかった状況も見えてくる。
インネパ店は本当に空気のように、当然のようにどこにでもある。じゃあなぜそこに存在するのか、そういう商売ができあがってきたのか、どんな人がオーナーやコックなのかっていうのは、インターネットにも載っていないでしょ」
――いつの間にか家系ラーメンを名乗る店くらいどこにでもありますけど、確かによく考えると不思議ですよね。
小林 「いわゆるガイドブック的な本ではなく、そんな話を集めた本を出せないかと編集者の島田さんに相談して、取材を進めることにしました」
 この本にGOを出した阿佐ヶ谷書院の島田さん。どうにか本の価格を3,000円以下に納めようと、涙ながらに削った原稿もあったそうだ。
この本にGOを出した阿佐ヶ谷書院の島田さん。どうにか本の価格を3,000円以下に納めようと、涙ながらに削った原稿もあったそうだ。
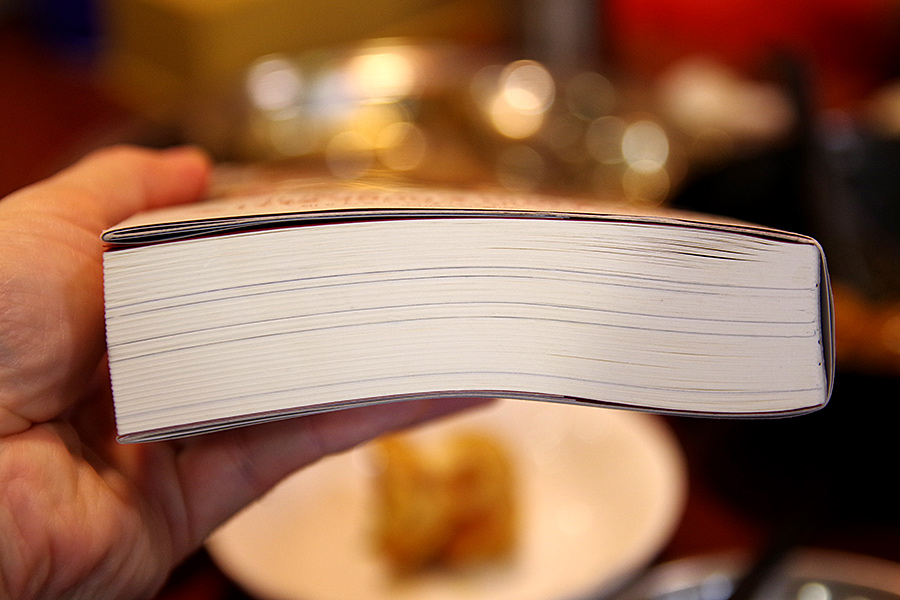 厚さが3センチを超えてしまったので、送料が高くて大変らしい。
厚さが3センチを超えてしまったので、送料が高くて大変らしい。
インネパ店の現在
この本には、北海道、東北、関東甲信越、中京、北陸、関西、中国、四国、九州、沖縄と南下しながら、地域ごとの特色やコミュニティの歴史だったり、その地に根を張って営むネパール人の紹介をメインコンテンツにしつつ、日本におけるダルバートの遍歴、インド・ネパール料理店の成り立ちなどを交えて詳しく紹介している。
主役は基本的にネパール人であり、インド人だけで構成された店の情報はあまり登場しない。「インド料理店とネパール料理店」ではなく、あくまで「インド・ネパール料理店」の本なのだ。
 グンドゥルックスペシャル(取っ手が付いた容器のチキンカレーも含む)、メニューにはない牛の脚のスープ(中央の丼)、ライス。
グンドゥルックスペシャル(取っ手が付いた容器のチキンカレーも含む)、メニューにはない牛の脚のスープ(中央の丼)、ライス。
小林 「僕の解釈だと『インド料理も出しているネパール人の店』がインネパ店。インド料理店という大きい括りの業態からスタートして、そこから枝分かれしたものです。
そもそもインドとネパールの間には国境こそありますが、陸続きなので料理に明確な境界はない。なだらかなグラデーションで構成されています。
どの料理をメニューに載せて、どれくらいネパール色を出すか。最終的にはオーナーの考え方によるんですけど、オーナーが理想に燃えて伝統的なネパール料理を出したくても、雇ったのがインド料理店で働いていたネパール人コックだと、ネパール料理を出したがらなかったりする。そんな料理は売れないよ、客を呼べないよって」
――タンドールを置いてナンを焼くべきだと。
 骨の周りのゼラチン質がうまい。本来は水牛で作る料理とのこと。
骨の周りのゼラチン質がうまい。本来は水牛で作る料理とのこと。
小林 「例えば最近オープンしたネパール料理に力を入れている店にある『ダルバート』は、『ダル=豆のスープ』と『バート=ライス』を組み合わせた言葉で、おかずや漬物がついてきます。ネパールでは『ダルバート=食事』くらいの代名詞的存在です」
――日本だと「ごはん」と「みそ汁」が付くと「定食」と呼ぶ、みたいな。
小林 「今の日本ならおかずにバリエーションがありますけど、じゃあ江戸時代、明治時代に一般庶民が何を食べていたかというと、毎日そんなに代わり映えのないものを食べていたはず。ご飯とみそ汁とお漬物で、たまに魚が登場するくらい。
日本人に馴染みのあるインド料理店のナンやこってりしたカレーが、レストランで食べる豪華な外食用として比較的最近登場したメニューであるのに対して、ダルバートはネパールの庶民の日常的な食事(家での食事だけでなく、長距離バスの休憩所の簡易食堂などで食べる)、ちょっと前の日本の食事のイメージなんです」
――レストランで食べるような料理ではないと。
小林 「だから日本で長く働いているシェフからしたら、ダルバートなんて庶民的すぎるから、レストランでお金を取って出す料理は非日常的の方がいいぞと否定する。彼らはインド料理を作れる技量に誇りを持っているので」
――海外で日本食の料理人に「納豆定食と卵かけごはんの店を作ろう」といっても、「寿司とか天婦羅を作らせろ!」ってなるのと一緒だ。
 プルジャダイニングでは料理の種類が多いこともあり、ダルバートという単語は使っていない。
プルジャダイニングでは料理の種類が多いこともあり、ダルバートという単語は使っていない。
――それでもダルバートを出す店が増えてきた理由はなんですか。
小林 「あまりにもインド・ネパール料理店が増え過ぎたから。地方だとまだ数が少ないので典型的なインネパ店が多いですけど、都市部だと他店と差別化をしなければいけなくなったのが大きい。
また長く日本に住んでいると郷土の味が懐かしくなってくる人もいるでしょう。お金のないネパール人留学生に安くダルバートを食べさせたいというオーナーも多いです。
――「家で食べるようなもの」だからこそ商売になることもある。
小林 「現地のダルバートをそのまま出すのではなく、ちょっとゴージャスなお皿に乗せて高級感を演出したり、肉料理を追加したり、お金がとれる料理にカスタマイズしている店もあります。ダルバートという名前だとライスとスープだけと思われるからとAセットとかネパールセットという名前にしたり。最近は日本人シェフが経営するネパール料理店も増えました」
――「OLD NEPAL」は日本人の店ですね。
小林 「今やOLD NEPALは新世代のネパール人オーナーが憧れる店です」
インネパ店の個性を探す旅
――この本では北から南へと店を紹介していますが、典型的なインネパ店にも地域ごとの特徴ってあるんですか?
小林 「どの店もハンコで押したように同じメニューが載っているけれど、ちょっと気になる部分をよくよく調べてルーツを探ってみる。すると独特の地域性にたどり着くことがあります。ちゃんとした暖簾分けではなくても、やっぱり働いていた店の特徴は引き継ぐものみたいです。
例えば名古屋周辺だとハンディというつぼ型の食器に受け皿をセットする文化がある。これはネパールだとやりません。その源流をたどると1軒の店にたどり着き、そこで修行したシェフが独立したときに作法として継承していた。福岡だったらカツカレーみたいにタンドリーチキンをカレーライスに乗せる店が多い。これも遡れば1つの店からスタートしています。こうやって重箱の隅をつつくのが楽しい」
――誰も調べようとしない食文化の歴史ですね!
小林 「インネパの歴史はせいぜい20~30年なので、何軒か回るとたどり着くんですよ。もうちょっと苦労させてくれって思うこともあります。
すごくおいしい店とか有名な店であれば、いろいろ記録が残るかもしれないけど、どこにでもあるような店のカレーセットにだって歴史はある。誰も興味ないかもしれないけれど、私にはそれがおもしろかった」
 グンドルックは干し野菜を発酵させたネパールの伝統食材で、プルジャさんは店で買うと高いからと、群馬や茨城に畑を借りて、大根、春菊、高菜、カリフラワーなどの野菜を育てて、自ら作った自家製グンドルックを出している。日本人にとっても懐かしさを感じさせてくれる味だ。こういう料理をおもしろがるお客さんがいてこそメニューは個性的になる。手間と希少性を考えると超激安。※残念ながら3/21で終了。
グンドルックは干し野菜を発酵させたネパールの伝統食材で、プルジャさんは店で買うと高いからと、群馬や茨城に畑を借りて、大根、春菊、高菜、カリフラワーなどの野菜を育てて、自ら作った自家製グンドルックを出している。日本人にとっても懐かしさを感じさせてくれる味だ。こういう料理をおもしろがるお客さんがいてこそメニューは個性的になる。手間と希少性を考えると超激安。※残念ながら3/21で終了。
――秋田の店にある「いぶりがっこチーズナン」は衝撃的でした。
小林 「そういうアイデアは往々にして、お客さんからの提案が多い。その店はオーナーがネパール人の主婦だから、子供のつながりで地元のおかあさんが友達で、メニューを一緒に考えてくれるんでしょうね。そういった日本人の入れ知恵で作っているメニューは各地で見え隠れしています。
オーナー側がローカライズに力を入れている場合もあります。北海道はスープカレーが主流だからとメニューに加えたり、名古屋ならエビマヨをサイドメニューに用意したり、横須賀では『よこすか海軍カレー』公式の海軍カレーを作ったり」
――ネパール人が作る海軍カレー!それは何味なんだろう。
小林 「インド料理店だったらこういう変化球は少ないけど、インネパ店は自由だから。良い意味でも悪い意味でもこだわりを持っていない人が多いんです。こだわりがないからインネパ店は全部同じメニューという印象を持たれていた。でもこだわりがないから新メニューにも躊躇がない。
日本人だと考えられない話ですが、例えばインネパ店を別の人が引き継ぐ場合、オーナーもシェフも変わるのだから店名もメニューも考え直しますよね。でも店名やメニューを変えたら看板や印刷物を変えるのにお金がかかる。だから店名もメニューもそのまま引き継ぎ、昔の写真とかをネットで見ながら食べたことのない前シェフの味に寄せるという場合が一部である。必ずしも店が自己実現の場だったり、料理人としての夢を叶える場所ではないんです」
――店は変わっていないのに従業員だけ入れ替わっている!客からしたらちょっとしたミステリーだ。
小林 「スナックの居ぬき店舗でソファーや内装はそのままなのに、メニューはやたらと本格的で何ページもあったりする場合もある。そういう個性がおもしろいんですよ」
 カリフラワーと豚のハラミの炒め物。豚は市場で大量に仕入れるため希少部位が食べられることも。小林さんは先日脳みそを食べたとか。
カリフラワーと豚のハラミの炒め物。豚は市場で大量に仕入れるため希少部位が食べられることも。小林さんは先日脳みそを食べたとか。
本場に近いネパール料理を国内で楽しめるのは日本だけの特権
――小林さんは食器屋であり、なおかつネパール語が喋れるので、ディープなネパールコミュニティ内の店にも入っていけるんだと思いますが、私みたいな一般人が入っても大丈夫でしょうか。
小林 「このアウェイ感が一つの楽しみですよね。食堂に見えない食堂とか。特別に日本人向けの対応っていうのはしていなくても、来てくれたらうれしいと思いますよ。日本人が来るということは拒絶をされていないということだから。
特にネパールの人は自分たちの料理を必要以上に卑下しているところがあって、日本人の口には合わないでしょって思い込んでいるので、おいしいといってもらえたら喜ぶはずです」
――前に新大久保のベッドガットという店に行きましたが、入っていいのかなという不安感があったけれど、行けば普通に接してくれて、すごくよかったです。
小林 「日本人ってかなり特殊なんですよ。例えばマレーシアにあるネパール人タウンの食堂には、ほぼネパール人しかいない。マレーシア人はネパール料理に興味がないから。イギリスなどもそうですね。
一方で日本人は食に対する好奇心が旺盛だから、日本語で書かれたメニューがないような店を逆におもしろがる一派がいる」
――確実にいますね。
小林 「ネパールの同胞向けに作った店なのに、想定外の日本人が来るパターンは外国ではなかなか見られない文化です。西川口あたりの中華料理店もそうじゃないですか。
でも少なくとも飲食店をやっているネパール人の店で、日本人お断りっていうところは1軒もなかったです。部外者は入ってくるなっていう感じではなく、常識をもって入店するならむしろウェルカムのはず」
 豚トロの炒め物。メニューにない料理も多いので、店員さんになんでも相談してみよう。
豚トロの炒め物。メニューにない料理も多いので、店員さんになんでも相談してみよう。
小林 「異文化との遭遇を楽しむならレストランとか食堂にいくのが一番手っ取り早い。言葉があまり通じなかったとしてもどうにかなります。
正直口に合わないと思う店もいっぱいあります。そういう場合は自分が試されている感じですね。この状況をどう楽しむか。おいしいとかまずいとか、安いとか高いとかの話だけではない。それだけだと表面的すぎる。食事の楽しみ方は何通りあってもいいんです」
 チャイ(甘いスパイス入りミルクティー)はネパール語だとチアと呼ぶそうです。
チャイ(甘いスパイス入りミルクティー)はネパール語だとチアと呼ぶそうです。
 すごくおいしかったです!また来ます!
すごくおいしかったです!また来ます!
こうして作者から直に話を聞けたことで、あのベタなカレーとナンのセットを表紙に持ってきた理由が分かった気がした。多くの人が食べたことのあるインネパ料理の裏に、これだけ厚みのある物語が存在していたという驚きを共有するためのセレクトなのだろう。
この『日本のインド・ネパール料理店』という本は、人生における楽しみ方、喜び方を教えてくれる本だ。例えば旅先で夕飯を食べる店を選ぶとき、一人だとつい失敗を恐れて無難な店に入ってしまうことがある。だが小林さんくらい価値基準に多様性を持たせることができれば、どんな店でも自分の中でエンタテインメントに消化することができるのだ。この本を読むことで、外食を今よりもっと幅広く、そして奥深く、心豊かに楽しめるようになるだろう。
紹介した本
定価:2,940円(2,700円+税)
紹介したお店
🍴プルジャダイニングもWEB予約がおすすめです🍺
※本記事に掲載された情報は、取材日時点のものです
※電話番号、営業時間、定休日、メニュー、価格など店舗情報については変更する場合がございますので、店舗にご確認ください
Source: ぐるなび みんなのごはん
巣鴨のプルジャダイニングでグンドゥルックを食べながら、小林真樹さんから「日本のインド・ネパール料理店」の話を伺う