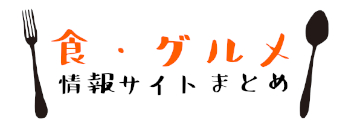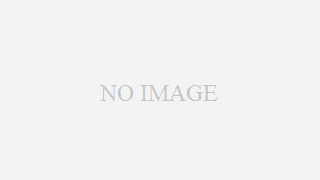古くからのオフィス街と最新の商業施設が共存する東京・日本橋室町の一角に「レストラン桂」はある。店頭のガラスショーケースには定番料理の食品サンプルが並ぶ。少々年季が入っており、いい感じに色褪せているのが、いかにも街の洋食屋然として味わい深い。
しかしそのかたわらに目を移すと、そこにはどこかフレンチビストロを思わせるような瀟洒(しょうしゃ)なメニューボードも置かれている。その内容は日ごとの定食メニューなのだが、その内容を見るとそれは、メインディッシュにライスとみそ汁がつくようないわゆる町洋食の定食というよりは、かつて日本のフランス料理においてコース料理に定食という訳語があてられていた時代のその「定食」を思わせるクラシカルな内容がつづられている。
扉をくぐるとそこはちょっとした異世界だ。
店内には純白のクロスがかかったテーブルが整然と並び、まさに「レストラン」の、少し背筋が伸びるたたずまい。しかし同時に目に入るのは、奥の酒棚にずらりと並ぶウイスキーや焼酎のキープボトルだ。夕暮れ時になると、この店は仕事帰りの男性ビジネスマンたちで活況を呈す。いわば紳士たちの社交場だ。彼らは生ビールやウイスキーのグラスを傾けながら、オーセンティックな洋食だけでなく、この店ならではの軽やかな「おつまみメニュー」を楽しむ。ときにはマダムを捕まえて洒脱(しゃだつ)な会話が繰り広げられる。ある意味本来の「ビストロ」つまりフランスの居酒屋が、すっかり日本化して根づいた光景と言えるのかもしれない。
紳士たちの社交場

そんな、レストラン桂が誕生したのは1963年。お店自体はその前から存在しており、ここともう1店舗、日本橋堀留町の店とともに別のオーナーが経営していた。ある時オーナーは「家賃が高すぎて儲けが出ない」という理由でここ室町店を閉店することに決めたのだが、そこでチーフを務めていた手塚正昭さんが大借金をして店の権利を買い取り、店は継続されることになった。それまでずっと店を取り仕切ってきた正昭さんにとって、愛着のあるこの店がそのままなくなってしまうのはあまりに忍びなく、また実際にお店には既に多くの常連さんがついていた。ここからレストラン桂の歴史は始まる。お店は正昭さんと奥様の清美さんを中心に、2人の兄弟もそれを手伝い、文字通り家族経営での再スタートとなった。
既にお客さんはついていたとはいえ、前オーナーが「儲けが出ない」と手放すくらいだから、経営は決して楽ではなかった。正昭さんは周辺の企業の会議弁当を請け負うなどして売上確保に努めたが、それでも苦しいことには変わりはない。そこで正昭さんが考えたのは「昼に来てくれるお客さんたちに夜も来てもらう」ということであった。幸い昼は忙しいビジネスマンたちがひっきりなしに来店し、当時150円のハンバーグと50円のライスなどを、ものの10分で平らげては次のお客さんに席を譲るような活況を呈していた。
当時レストラン桂はいかにも正統派の高級西洋料理店らしく、夜はフランス料理のコースも提供していたが、それだけでは日常使いにはそぐわない。正昭さんはビールやウイスキーなどのお酒を積極的に提供するとともに、お客さんの要望には柔軟に応え、店にある洋食の食材をフル活用して「焼き鳥」や「レバニラ」など、当意即妙に「つまみ」を提供した。そしてそれだけではなくカワハギやいわし丸干しなど洋食屋らしからぬつまみも置いた。いうなれば洋食屋でありつつ居酒屋でもある、というレストラン桂の独特なスタイルがその時点で完成したというわけだ。昼は10分でそそくさと食事を済ませる人々が、仕事を終えると今度はゆったりとした時間の中で1日の疲れを癒す。レストラン桂はこの日本橋室町になくてはならない店となった。
現在この店には、いかにもレストラン的な重厚さをたたえるメインメニューのほかに、「自慢のいっぴん」と題された裏メニュー的な小メニューがある。そこにはメインメニューからこぼれた正統派洋食メニューに加えて、そんな当時からの「おつまみメニュー」が並んでおり、それらは今も夜毎にここに集う紳士たちの心をガッチリ掴んでいる。
看板メニュー「海老フライ」のスゴさ

とはいえもちろんこの店の主役は、愚直なまでに丁寧に作り込まれた伝統の洋食メニューだ。いまどき珍しくカップではなくスープ皿でたっぷりと供されるコーンポタージュは、ただ甘いだけでないどこか気品のある味わい。ビーフシチューやタンシチューはいかにも「東京の洋食」らしい、とろける柔らかさをどっしりとしたデミグラスソースが引き立てる王道のおいしさだ。
キリッと効いたナツメグなどの香辛料が懐かしくも華やかなごちそう感を演出するハンバーグや、洋食店ならではの繊細な火入れが楽しめる牛ロースステーキも定番の人気メニュー。
中でもこの店のスペシャリテともいえる珠玉の一品が海老フライだ。
海老フライという料理はほとんどの洋食屋において花形的存在だが、この店のそれは日本でも屈指だと私は思う。この店にしては決して安くはない価格だが、それであっても原価が心配になるような立派すぎる有頭エビが使われている。
「日本で一番大きな海老フライなんじゃない?」という常連客もいるという。たしかに、切り込みを入れて無理に長さを伸ばしたりコロモで上手に太らせたりした巨大海老フライみたいなものを除けば、本当に日本一かもしれない。
料理というものは何でも、大きければいいというものではないが、こと海老フライに関しては、その太さが確実においしさに影響する。香ばしく揚がったコロモからじんわり火が通った中心部分に至る、カリッ、みしっ、しっとり、という魅惑のグラデーションが、熟練の揚げ技術で創出されるのだ。
大きな海老の頭にパンパンに詰まった海老ミソもまた魅力だ。有頭エビの頭が高級感を演出するための飾りに過ぎないと認識している人は少なくないかもしれないが、この有頭海老フライを食べたらその認識は確実に変わるのではないだろうか。有頭だからこそのミソの旨味と脚の香ばしさ。海老フライの頭と身が接する部分をナイフで切り取って頬張る一口がこの料理のクライマックス。切り取った頭はぜひ手掴みで、その奥の奥まで余すことなくしゃぶり尽くして欲しい。
ちなみにこの海老フライを2人で1皿オーダーすると、それは最初から付け合わせやタルタルソースとともに2皿に分けて提供される。こんなところにもこの店のレストランとしての矜持がひしひしと感じられるし、実際それによってこの店のスペシャリテに邪念なくじっくりと向き合えるのは、ただただ嬉しいひとときだ。
ジャンルは違えど飲食業という同業者である私の目から見ると、この店の料理はそこにかかる手間や技術、加えてズバリ食材原価から考えると、正直言って安すぎる。
創業者である手塚正昭さんからこの店を引き継いだ息子の清照さんに、その感想をあえて率直に投げかけてみた。飲食店に対していたずらにその安さだけを称賛することの愚は、同業者として充分すぎるほど承知はしているわけだが。
「このあたりは次々に新しい商業施設や飲食店もできてどんどん生まれ変わっていくなかで、ウチが昔ながらの効率の悪いやり方を続けてるのは自分でもバカだな、とも思います」と、清照さんは笑う。
そして、「でも大丈夫。原価も含めてちゃんと利益は出てますよ」とも。
それは清照さんを中心とする熟練した職人の手際のよさが手間を圧縮しているとも言えるし、洋食店には珍しく、お酒でしっかり利益を確保できているこの店のビジネスモデルが全体として適正な利益を生んでいるとも言えるだろう。老舗恐るべし……。
ママさんは店の顔

この店の魅力は、そんな本来の意味での「コストパフォーマンス」を体現している安くておいしい料理だけではない。創業者の奥様であり、この約60年ずっと接客の中心だった清美さんの存在は、もはや店そのものと言っても過言ではない。
関西出身の清美さん、通称「ママさん」は、とにかく常連客に愛されている。酒も入って上機嫌な常連さんたちは、いつもくるくると忙しく立ち働くママさんに気をつかいつつ、少しでもチャンスがあるとすかさず話しかける。しかしそんなときの清美さんはあくまでクールだ。さらっと会話を切り上げるとまたすぐ仕事に戻る。知らない人から見るとその姿は、今の言葉で言う「塩対応」とすら見えてしまうかもしれない。でも当の常連さんたちはとても嬉しそうだ。
「あたしは愛想がないからね」と、清美さんは言う。
「昔のお客さんはみんな定年でいなくなって、気がついたらみんな年下。あたしはそんなお客さんたちに友だちとして接してるだけ」とも。そんなさりげない一言に、生涯「看板娘」である清美さんの、サービスパーソンとしての魅力がにじみ出ている気がした。昨今の飲食店の、元気で丁寧でいつだってお客さんを立て続ける接客技術はもちろん素晴らしいものかもしれないが、実はそんなものはなくたって「お友だち」を思いやる気持ちは過不足なく伝わるのだ。ましてや過剰なサービスなどそもそも不要で、そこにあるのはお店とお客さんのフラットで自然な信頼関係。ある意味これからの飲食店が目指すべきことなのかもしれない。
私が初めてこの店を1人で訪れたとき、「ママさん」のあくまで淡々としたクールな接客に若干の緊張を強いられたのは事実だ。しかし、店内を埋め尽くす紳士たちとママさんの自然体なやりとりを眺めているうちに、その空間はとても心地よいものに感じられ、いつしか心からリラックスしていた。
これは完全に余談なのだが、その初回訪問の最後お会計のとき、ママさんはレジのキーをリズミカルに叩きながら私の足元にチラッと目をやり、「いい靴やね」と言って、初めてニッと笑った。私はその日たしかに、お気に入りのちょっと派手な靴を履いていた。不意を突かれた私は、あっどうも、とぎこちなく返しながら心の中で、「ツンデレかよ……」とニンマリしつつお店を後にした。
この街になくてはならない店
そんな「紳士たちの社交場」であるレストラン桂にも、実は少しずつさらにいい変化が訪れている。
2代目である清照さんは、「昔に比べると、女性のお客さんはずいぶん増えました。おひとりで来られる方もたくさんいらっしゃいます」と、嬉しそうに語る。10年ほど前にオシャレな大規模商業施設ができたこの街は、明らかに人の流れが変わり、そんななかこの渋すぎる老舗を訪れる新しいお客さんも徐々に増えていった。その商業施設やその周辺には、最新のいかにもオシャレな飲食店も激増したわけだが、その中からこのレストラン桂を選ぶ人々に対し私は「お目が高い」という賞賛を送りたい。
そんなこの店にも、当然ながらコロナ禍は手痛い影響を与えた。創業時からずっと経営の生命線であった夜の営業がままならない日々。しかしそんななか、とある近隣の会社は、先払いの食事券を発行してその資金繰りを支えたという。創業期以来ずっとこの街になくてはならない存在であり続けたレストランの窮状を、放っておくことなんてできなかったのだろう。
「きっと皆さん戻ってきてくれると信じています」。清照さんは安堵の表情を浮かべつつ「だから少なくともあと10年は頑張ってもらわないと」と、母親であるママさんを見遣る。
当の清美さんは息子のそんな言葉を聞いて「うふふ」と笑った。
紹介したお店
※本記事に掲載された情報は、取材日時点のものです
※電話番号、営業時間、定休日、メニュー、価格など店舗情報については変更する場合がございますので、店舗にご確認ください
著者プロフィール

鹿児島県出身。京都大学卒業後、食品メーカー勤務などを経て円相フードサービスを設立。多ジャンルの飲食店を経営する傍ら、食文化に関する著書も手がける。最新刊に『人気飲食チェーンの本当のスゴさがわかる本』(扶桑社刊)
Source: ぐるなび みんなのごはん
正統派レストランでもあり居酒屋でもある存在――日本橋室町「レストラン桂」の独特なスタイルについて