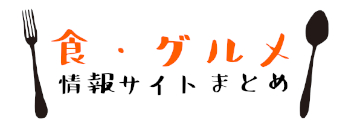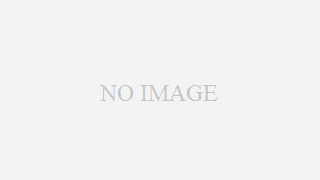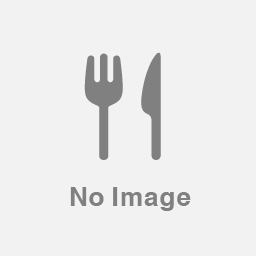独特なスタイルを持つ洋食店

東京は全国でも特に昔ながらの洋食店の多い街であり、その店々の多くには、どこか共通する一定のスタイルのようなものがある。ポークカツレツや各種フライもの、ビーフステーキやポークソテー、そしてビーフシチューあたりが看板メニューで、昨今だとハンバーグやオムライス、ナポリタンあたりも欠かせない。伝統的なメニューの味の決め手は、なんといっても濃厚なデミグラスソース。
定食類は、特に庶民的な店ではスープではなくみそ汁がつくのもお約束だ。そういうお店では、何種類かの料理を目玉焼きやサラダと共に一皿に詰め込んだ「大人用お子様ランチ」的な趣の盛合せ定食が「Aランチ」「Bランチ」といった名称で提供されていることも多い。
こういった典型的なスタイルは、もちろん東京だけにとどまらず全国にも波及しており、我々が「洋食屋さん」と聞いてまずイメージするのは、そういうお店だ。
そんな東京のど真ん中新宿に、創業60年にもなろうとする一軒の洋食屋がある。アカシアという名のその店は、しかしそういった東京スタイルの洋食屋とは、どこか、いや、はっきりと異なる。もちろんビーフシチューやハヤシライスといった王道の洋食メニューも取り揃えているが、この店で圧倒的に人気のあるメニューは「ロールキャベツシチュー」だ。ポークカツも目玉焼きハンバーグもナポリタンもないし、定食にみそ汁はつかない。
新宿という日本有数の繁華街にあり毎日多くのお客さんが訪れるアカシアは、東京を代表する人気の老舗洋食店の一つと言えるだろう。しかしそのスタイルは実はかなり個性的なのである。
1963年、アカシア誕生
アカシアの創業者である鈴木邦三さんは終戦後、家業の魚屋を継いだ後、食べ物屋に転身した。最初はラーメン屋、そしてその後その店を定食屋に切り替えた。
「どちらもずいぶんと当たったようですよ」
と語るのは、創業者の邦三さんの孫にあたり、現在のアカシアを取り仕切る鈴木祥祐さん。
邦三さんは料理に関してほぼ独学ながら、とにかく料理が好きで、また商家の出身ということもあり商売の機微にも長けていたようだ。
その後、邦三さんはまたもや商売替えを行う。ラーメン屋、定食屋と来て今度は洋食屋である。当時はいうなれば洋食屋の黄金期。洋食は外食産業の花形であり、東京では次々に新しい洋食屋がオープンしていた。邦三さんはそういった店を食べ歩いては研究し、またしても独学で洋食屋「アカシア」をオープンした。1963年のことである。
しかし残念ながらその業態転換は決して順調ではなかった。東京オリンピックの開催を目前にして、外国人観光客の増加や景気の上向きを見据えた邦三さんは、洋食店アカシアを周りの店よりちょっとばかし高級な店と位置付けてオープンさせたのだが、もしかしたらそれは時代を少しばかり先取りしすぎていたのかもしれない。
「ラーメン屋や定食屋時代と比べてお客さんはガクッと減ってしまったそうです」
と、祥祐さんは祖父から聞いた当時の話を語る。
開店当初のアカシアは、ステーキや海老フライを中心とする「高級洋食店」だった。いうなれば東京洋食の典型的なスタイルの一つである。しかし価格設定の高さが災いしたのか、2か月、3か月と泣かず飛ばずの状況が続く。しかしその時、邦三さんにあるアイデアが閃いた。それがその後から現在に至るまでアカシアの看板メニューとして多くの人々に愛され続けているロールキャベツである。
ロールキャベツシチューは家庭の味

実は邦三さんにとってロールキャベツは、子供の頃から慣れ親しんだ「家庭の味」だった。
まだ「戦後」とも言っていい時代の家庭料理がロールキャベツというのはずいぶんハイカラな話だが、よくよく考えるとロールキャベツは、少量の挽肉さえあれば後は野菜だけで賄える実に家庭向きな料理。邦三さんの母は終戦後間もない横浜の、外国人の来訪も多かった、とある上流家庭でその作り方を学んだそうだ。
邦三さんの母は朝まとめてこれを作っておき、そのまま仕事に出かけた。子供たちは夜、両親の帰りを待ちながらこれを温め直してご飯と一緒に食べた。一皿で肉と野菜がバランスよく摂れて、しかもご飯によく合う味付け。身も心も温まる鈴木家の家庭料理は、まさに母の愛であり、そしてそれがその後アカシアの経営危機を救うことになった。
邦三さんはこのロールキャベツを、ライスと組み合わせたセット、つまり少年時代の邦三さんが家で食べていたのとまったく同じシンプルなスタイルで提供した。この時のライスは、東京の洋食店としては珍しく、皿ではなく茶碗で提供された。これももしかしたら子供の頃から慣れ親しんだ家庭料理へのオマージュだったのかもしれない。温かさが身上でもあるロールキャベツに付くライスを「皿より冷めにくい茶碗で」というのは確かに理に適ってもいる。
高級洋食店だったはずのアカシアに突如登場したロールキャベツとライスのセットは、120円という安値で提供された。それは当時のタクシーの初乗り料金と同じだった。
「それくらいの値段だったらさすがに多くの人にも食べてもらえるだろう」
という邦三さんの読みは、今度は見事に当たった。
ロールキャベツといえば誰もが知る洋食メニューの一つだが、これが洋食屋で提供されることは実はまれである。洋食はあくまでフランス料理、ないしは英国式フランス料理が主なルーツであるが、ロールキャベツはもともとその系譜にはない。どちらかいうとドイツからロシアにかけての東欧のイメージか。
いずれにせよロールキャベツは、もともと、レストランの料理ではなく家庭料理として日本に入ってきたようだ。少量の肉を大量の野菜で「かさ増し」して経済的に作ることもできるという意味で、コロッケほどではないにせよ庶民的なイメージもあっただろう。現代では洋食メニュー全般にすっかり「庶民的」なイメージがついてしまっているので、そのあたりの感覚の差はイメージしにくいかもしれないが。
創業間もない高級洋食店アカシアでは、ロールキャベツのそんな「洋食にしては庶民的」なイメージを逆手にとって、それをあくまで庶民的な価格で売り出し、またたく間に大人気を博したというわけだ。
もちろん人気の理由は安さだけではなかった。うまいし、よその店には似たものがないし、そしてどこか「ヤミツキ」になる味わいがあったからだ。
アカシアのロールキャベツは正確には「ロールキャベツシチュー」という名前でオンメニューされている。その名の通り、とろりとしたクリームシチュー風の見た目だ。私がこのロールキャベツシチューに初めて出会ったのは今から5年ほど前のこと。もちろんその時点ではこのメニューが創業者の母の味を再現したものであることなど知る由もない。
アカシアのロールキャベツシチュー、その独特なおいしさの秘密とは

見た目からいかにもミルキーなホワイトソース的味わいを予想しつつ、まずそのソースを口に運んだ私はびっくりした。確かにまったりとしたまろやかさはあるものの、ミルク感は皆無だったからだ。これは牛乳ではなくロールキャベツを煮込んだスープに小麦粉を炒めたルーでとろみをつけたものであろうということはなんとなくわかった。今ではあまり見られないクラシックな技法だ。しかしそれであっても、ルーには必須であるはずのバターの風味もない。そしてこういう古典的な煮込みに付き物のナツメグ、クローブ、ローレルといった香辛料の風味もない。ソースはひたすら肉と野菜の旨味が凝縮し、それが渾然一体にまとまった味わいだった。シンプルな塩の味がそれをキリッと引き締め、確かにご飯が欲しくなる。あえてわかりやすく言うとラーメンの白湯(ぱいたん)スープを限りなくエレガントに仕立てたような味。
ちなみに現在のアカシアを取り仕切る三代目の鈴木祥祐さんは逆に、博多で初めて豚の臭みを抑えたタイプの豚骨ラーメンを食べたときに「これはウチのロールキャベツに通じるものがある」と驚いたそうだ。
ロールキャベツ本体は子供の握りこぶしほどもある大きさで、ナイフを入れるとスッと抵抗なく切れ、ねっとりとまとまった肉ダネがきっちりと中心に巻かれた見事な断面が現れる。この店の常連客はこれをナイフ・フォークは使わずスプーン一本で食べ進めるという話を後に聞いたが、それも納得の柔らかさだ。そして単に柔らかいだけではない。普通ロールキャベツをスプーンのみで食べようとすると、それが充分柔らかく煮込まれたものであってもキャベツはすぐにバラバラになる。しかしこのロールキャベツはそうはならない。スプーンの縁で切断してそれを口に運ぶまで、一体感は維持される。
そんな、どこにでもありそうで実はここにしかないロールキャベツの作り方を、祥祐さんは惜しげもなく教えてくれた。
肉ダネは牛豚の合挽き肉に玉ねぎと少量のニンニクが加えられる。それを巻くキャベツは、球の中心近く、中葉、外葉、と小・中・大の順番できっちりと巻かれる。材料の無駄を出さずなおかつ均等にきっちり巻きあげる合理的な職人技だ。
大鍋に隙間なく並べられたロールキャベツは、チキンブイヨンで煮込まれる。まずは2時間、1時間冷まして味を浸透させてからまた2時間煮込む。キャベツは型崩れすることなく柔らかく仕上がり、牛・豚・チキン、そして野菜の旨味が凝縮したスープも同時に完成する。
そのスープにとろみとコクを与える小麦粉のルーには、バターではなくラードが使われる。これは創業者・鈴木邦三さんの母の作り方そのままだ。
「当時の一般家庭ではバターなんておいそれと手に入らなかったからでしょうね」と祥祐さんは語る。言わば最初は「代用」だったのかもしれないが、実はこれがこのソースに個性を与えている。
「なにしろバターはおいしすぎるからね」と祥祐さんが言うのももっともで、ラードだからこそ肉と野菜の純粋な風味を覆い隠すことなくソースにコクを与える。ラーメンを思わせるようなヤミツキになる味わいも、このラードによってもたらされているところもありそうだ。
老舗の進化
レシピは創業以来基本的には変わっていない。ただし近年になって煮込む際にローレルを2枚だけ加えるようになったそうだ。加えると言っても大鍋に2枚だからごくわずかな量である。常連客にも変化を気付かれないようにしつつ細かいアップデートは欠かさない、これがいつだって老舗の老舗たる由縁だ。
「レシピは変わってないけど、肉は昔に比べて格段においしくなりましたね」と、祥祐さんは言う。
そしてさらに「昔から馴染みの肉屋さんが、ときどき在庫の関係とかで和牛とかのすごくいい肉を持ってくるんだよね。それで作ると確かに抜群にうまいんですよ」とも。だから運のいいお客さんは時に普段よりさらに「抜群」なロールキャベツに出会えるということになる。
「だから肉屋さんには『あんまり和牛は持ってくるな』って言ってるんですよね。お客さんが次来た時がっかりしちゃったら困るんで」。
ロールキャベツシチューは創業当時から現在に至るまで、押しも押されもせぬアカシアの名物である。単品は「二貫」だが、「一貫」のハーフサイズもあり(この「貫」という数詞がまた実に味わい深い)、そしてその「一貫」と他の料理を組み合わせたセットメニューが数多くある。
その中でも、ロールキャベツシチューとカレーをライスの左右に「合いがけ」にした一皿は、何かイケナイことをしているかのような悪魔的魅力を放っている。アカシアのカレーは2種類あり、どちらもカレー専門店にもまったく引けを取らない絶品なのだが、その中でも特に「極辛カレー」と銘打たれた骨付きチキンのスパイシーなカレーは、おそらく食べた人誰もが驚く逸品だ。これを作ったのが先代の鈴木康太郎さん。創業者の息子さんで、祥祐さんの父にあたる。次はこの「極辛カレー」の誕生秘話から筆を起こそう。
紹介したお店
※本記事に掲載された情報は、取材日時点のものです
※電話番号、営業時間、定休日、メニュー、価格など店舗情報については変更する場合がございますので、店舗にご確認ください
著者プロフィール

鹿児島県出身。京都大学卒業後、食品メーカー勤務などを経て円相フードサービスを設立。多ジャンルの飲食店を経営する傍ら、食文化に関する著書も手がける。最新刊に『人気飲食チェーンの本当のスゴさがわかる本』(扶桑社刊)
Source: ぐるなび みんなのごはん
あの“スプーンで切れるロールキャベツ”は、どうやって生まれたのか―― 新宿の老舗洋食店「アカシア」の60年[前編]